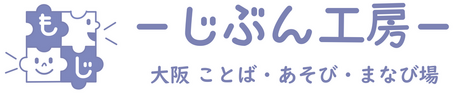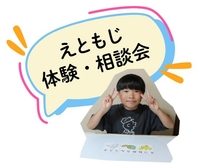- ホーム
- じぶん工房のひとりごと
- じぶん工房の教材「えともじ」
じぶん工房の教材「えともじ」
2024/08/30こんな使い方で学習を支えています
こんにちは!
こども言語聴覚士 さいとう です
夏も終わりかけていますね。
私が幼少期から結婚するまで住んでいた箕面では、自然が多い為かセミが容赦なく叫んでいて、それはそれはうるさかったのです。
9月にさしかかると、「ツクツクボウシ」が泣き出して、やっと夏が終わるな~と、寂しくなったりもしていました。
こども言語聴覚士も、夏休みは忙しく、いつもより3人程多く子どもさんたちとの言語指導が多いです。
そんな中、「えともじ」はこんな風につかってみるのもいいよ!を
お伝え出来たらと思っています。
「えともじ」のとっかかりはこんな感じで遊ぶといいかも
「グリコ」知ってる?
言語指導で、音韻意識が芽生えてくると、
ゲーム性の高い言葉の遊びが楽しめる様になります。
「しりとり」とか「グリコ」とか、、
「グリコ」って遊びは知っていますか?
40代オーバー世代は、長い階段を見ると「グリコ」を思い出します。
じゃんけんで
「グー」…「グ」「リ」「コ」の3文字だから3歩
「チョキ」…チョコレートの「チ」「ヨ」「コ」「レ」「イ」「ト」の6文字の6歩
(音韻意識的には?なのだけど←これについてはまた後日)
「パー」…「パ」「イ」「ナ」「ツ」「プ」「ル」の6文字だから6歩
じゃんけんをして勝った人が、出した手の文字数だけ階段を上がれるという、昭和の遊びです。
負け続けた人は、だんだんはなれていく、、、経験あると思います。
そんな遊びができるようになるのが、4歳以降に芽ばえる「音韻意識」なんです
「グリコ」ができる前に
とはいっても「グリコ」をいきなり遊びに入れ込む前には、1文字の音と文字が対になっている事や、1拍の長さを感じる事が大切になってきます。
「グリコ」が「グーコ」だと、2拍と感じてしまいますが、手を叩きながら見本をみせる、楽しくなるとマネっコする、などで
音と1拍を意識したり、文字を頼りに理解がうながされ音韻意識を促すと経験上感じています。
「えともじ」は音韻意識が芽生える前からつかえる教材
じぶん工房が企画・制作している「えともじ」は音韻意識が芽生える前から遊べる教材です。
音韻意識の課題を実施する前には、実際に目の前にある物を認識しているかどうかをみる必要があります
例えば、絵本のリンゴの絵と、実物のリンゴが一緒の物だ!といった理解ができているかと、いうところです。
えともじの初めのステップとして5つあります


上記の様に、各ステップで何度か遊ぶ事で、「え」と「もじ」をつながる遊びができてきますよ
また、言語聴覚士のひとりごと。お付き合いください
関連エントリー
-
 はじめまして!こども言語聴覚士のさいとうです!
じぶん工房の紹介 はじめましてこちらのホームぺージに来ていただきありがとうございます3児の母で14年
はじめまして!こども言語聴覚士のさいとうです!
じぶん工房の紹介 はじめましてこちらのホームぺージに来ていただきありがとうございます3児の母で14年
-
 おしゃべりを諦める?
言語聴覚士をしていると、言葉を引き出してくれる専門家だと思われていることが多いと思います 時々、言葉
おしゃべりを諦める?
言語聴覚士をしていると、言葉を引き出してくれる専門家だと思われていることが多いと思います 時々、言葉
-
 ベビー色彩知育🄬インストラクター 取得しました!
やっと、、やっと、、、やっと取れました!ベビー色彩知育🄬インストラクター ベビーの可能性を感じられる
ベビー色彩知育🄬インストラクター 取得しました!
やっと、、やっと、、、やっと取れました!ベビー色彩知育🄬インストラクター ベビーの可能性を感じられる
-
 裏舞台のキラリ
毎年、大阪市では、こども会育成連合会主催のこども文化祭があります!当方の学校では、クラブ・同好会とし
裏舞台のキラリ
毎年、大阪市では、こども会育成連合会主催のこども文化祭があります!当方の学校では、クラブ・同好会とし
-
 はじめてのマルシェ出店
3月末に満開になった桜も、4月のはじめには散り始めて、、儚さを感じています。そして、もう4月! 1月
はじめてのマルシェ出店
3月末に満開になった桜も、4月のはじめには散り始めて、、儚さを感じています。そして、もう4月! 1月
-
 祝!商標登録できました!
もう、あっという間に梅雨いりしましたね。みなさん、お元気に過ごされていますか?本日、「えともじ」の商
祝!商標登録できました!
もう、あっという間に梅雨いりしましたね。みなさん、お元気に過ごされていますか?本日、「えともじ」の商