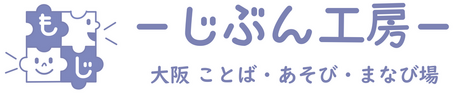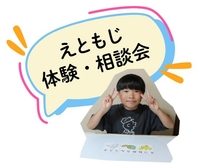斉藤 訓子(さいとう くにこ)
まちのこども・こうさく言語聴覚士

言語聴覚士×デザイン×アートをつなげてじぶんらしさを引き出すサポートをしたいと思っているセラピストです。
芸術が好き、デザインが好きで、芸術やデザインを通して人の役にたてる事ができればと思ってセラピストになりました。
じぶんのペースで、じぶんらしく、このままの私を大切にしながら
楽しく面白くしあわせにすごしてもらいたいと、願っています。
| 出身地 | 大阪府 箕面市出身 自然が多くてサルも遊びにきます |
|---|---|
| 出身校 | 被昇天幼稚園 萱野北小学校 箕面第二中学校 東豊中高校 浪速短期大学 大阪芸術大学 大阪医専(夜間) |
| 血液型 | 日本人に共通点の多いA型 |
| 資格 | 国家資格 言語聴覚士 |
| 資格 | おもちゃインストラクター kashiko™発達色彩インストラクター 認定講師 |
| 趣味 | 最近始めたバレーボール(9人制) |
| これは自慢だ | 何でも笑う!! |
| 休日の過ごし方 | 漫画を見る、映画をみる、たしなむ程度のお酒。にゃんこと戯れる事 |
自分に自信がないけど、自立心は人一倍
3人兄弟の末っ子長女として生まれ、末っ子特有の自由な子育ての為か、楽しく過ごせたらいいんじゃない?とやりたい放題やっていました(笑)ある日何気なく描いた鳥のイラストを母親が大絶賛してくれたことがあり、母親は本気ですごいと言っているな、、と感じ、絵を描く事が好きになり、得意になりました。
大学卒業までこれといって大きな困難もなく過ごしましたが、当時は就職氷河期で就職なんて同級生の中での数人程度。私もバイトからインテリアの床材の卸の仕事を始め、若さゆえうまくいかない日々を過ごしていました。そんな時に父親が営んでいた会社に呼ばれ、事務員として働き始めました。話を聞いていると経営が傾いているとのことで、だんだん会社が傾いていく様子を身にしみて感じ、女性が自立する事も必要と考え、資格を取るきっかけになりました。
こどもSTとしてのこども成長のすばらしさを感じまくる
言語聴覚士として働き始めて、1年後に妊娠出産を経験しました。こどもの成長に喜びも感じながらも、しんどい思いもたくさん経験してきました。自分のやりたい事ばかりして過ごしてきた中で、子育ては自分の考え方や性質事態を違う角度に捻じ曲げるような感覚でした。
あぁ母親になるという事はこういう事かと感じました。今目の前にいるわが子を支えるのは私しかいないと思うと、わけもなく悲しくなったり、うれしい感情もあり、心か忙しかったとうっすら記憶しています。
たまたま私はこどもの言語聴覚士であり、こどもの成長の知識をすこし持っていたことから、乳幼児、幼児期の不思議さを、まだ前向きに捉える事ができ、こどもの成長はすばらしいと感じる事が多かったと思います。
そこから子供たちの成長の過程を知る事は、子供と大人をお互いに尊重し合えるエッセンスになると感じ始め、子供の成長の奇跡を大人に知ってほしいと思うようになりました。
「これ、わたしが作るんですか?」ママの一言から
こども言語聴覚士(以下ST)をしばらくやっていると、こどもの遊びの中から今できる事や課題を見つける事が多く、親子での遊び方を説明し共感する事がいかに大切であるかという事を保護者に伝える機会をいただき、ことばの悩み事を通して親と子の関係を改めて考えるきっかけになりました。私自身、教材やイラストで説明したり、ST指導にたくさん遊びの要素を入れ込んでいます。
ある日、教材を通してことばの説明をすると、付き添いのママより「これ、わたしがつくるんですか??」といわれ、
そうか、、、こどものことばの教材・おもちゃに出会う事って少ないな、、どんな遊び方をする事でどんな能力をみているとか、親御さんはわからないかもしれないと衝撃をうけました。
教材の案はあったが、量産が難しい中の出会い
ECサイトでハンドメイド教材として言語聴覚士が考えた「えともじ」を販売してると時々1人でのハンドメイドでは請け負えないくらいの量の注文がある時があり、毎日徹夜で作ったりする事が増え、何日もお待たせする事も増えてきました。 そこで、できるだけ家から近くで、紙について詳しい工場に声をかけてみようとおもいたち、いくつかの業者さんに声かけをしました。しかし、このパズルはできない、、との返事が多く、やっぱり自分で作っていくしかないかと思っていました。
偶然となりの区で営まれている紙業工場の社長に相談したところ、私が作ったパズルに関心をもってくださいました。
社長自身の妹さんもことばが遅く病院に通っていた事があったとのことで、ことばの発達をうながすおもちゃに興味をもってくださいました。
そこから、丈夫な素材や加工についても相談に乗っていただき言語聴覚士が作った「えともじ」ができあがったのです。
今では口コミでだんだんと広がり、沖縄から北海道の言葉の教室の先生や、言語聴覚士の先生、児童発達支援事業所の先生方から要望いただいております。